お子さまの成長に伴って、気になってくることの一つに「成績」があります。
「この子は頭の回転が速いな」と感じる子もいれば、「少し勉強が苦手なのかな」と感じる子もいて、それぞれに個性があります。
わが子の成績や勉強に関して、日々悩んでいるお母さまも少なくありません。
今回は、「勉強が得意な子・苦手な子」の違いや、保護者としてできるサポート方法について、一緒に考えてみましょう。
優秀な子に共通する家庭環境とは?4つの特徴
子どもが勉強に意欲を持つようになるには、もちろん本人の努力も大切です。
しかし、成績が良い子どもたちの多くに共通しているのが、「家庭環境」の影響です。
では、どのような家庭環境で育った子が、学力を伸ばしやすいのでしょうか?
ここでは、成績が優れている子どもに見られる家庭の共通点について考えてみましょう。
子供の自主性を育てようとしている
子どもに親の思い通りの道を無理に進ませようとしても、子どもは受け身になってしまい、自主性はなかなか育ちません。
自主性を伸ばすためには、親の「させたいこと」を一方的に押し付けるのではなく、子どもの気持ちや考えを尊重する姿勢が大切です。
とはいえ、何でも自由にさせて関わらない「放任主義」になってしまうと、それもまた自主性を育む妨げになります。子どもは方向性を見失い、成長に必要な支えを得られなくなってしまうからです。
子どもの意見をしっかりと受け止め、そのうえで「自分のことは自分で決める・行動する」機会を与えつつ、親も必要なときにはサポートする——
このようにバランスの取れた関わり方をしている家庭では、子どもの自主性が育ちやすく、その結果、学力や成績も自然と伸びていく傾向があります。
とにかく子供を褒める・否定的な言葉を使い過ぎない
子どもはたくさん褒められることで、やる気が高まり、自己肯定感も育ちやすくなります。
テストの点数や結果だけで評価するのではなく、勉強に取り組む姿勢や努力の過程を認めてあげることも大切です。
たとえば、宿題のノートが以前より丁寧に書けるようになったときには、
「前よりもノートがきれいに書けるようになったね」
と声をかけてあげるとよいでしょう。
また、難しい問題に挑戦して自分の力で解けたときには、
「この問題、難しかったのに解けたね。よく頑張ったね」
といったように、具体的に努力や成長を認める言葉をかけることで、子どもは自信を持ちやすくなります。
たとえ成績が一時的に下がったとしても、自信を失わず、勉強に対して前向きな気持ちを持ち続けることができるでしょう。
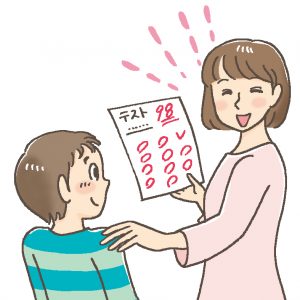
親子間でのコミュニケーションが活発
日常の何気ない親子の会話や一言が、実は子どもの学習姿勢に大きな影響を与えることがあります。
親との会話があることで、子どもは「自分は信頼されている」と感じ、心に安心感が生まれます。
日頃からしっかりとコミュニケーションを取っていると、子どものちょっとした変化にも気づきやすくなります。
親も子どもの様子をよく観察し、変化に敏感でいられるよう意識しておくことが大切です。
子どもが愛情をたっぷりと感じ、親への信頼感を持つことで、自然と学習に対する意欲が高まり、成績の向上にもつながっていくのではないでしょうか。
様々なことを子供に考えさせる
成績が良い子どもを育てているご家庭には、共通して「子どもと一緒に考える」「子ども自身に考えさせる」姿勢を大切にしている親御さんが多く見られます。
たとえば、勉強の計画を子ども自身に立てさせたり、テストで高得点を取るための工夫を一緒に考えたりすることが効果的です。また、ニュースを見ていて分からない点があれば、親が丁寧に説明したり、「あなたはどう思う?」と問いかけて、子ども自身の意見を引き出すことも大切です。
こうした日々の中で、子どもが自分の頭で考え、言葉にしてアウトプットする機会を持つことで、思考力や判断力が自然と鍛えられていきます。
親子で対話しながら学びを深めていく姿勢が、学力向上につながる一つの鍵となるのではないでしょうか。
勉強嫌いは親のせい?勉強しない子供の親に見られる3つの特徴
子供が勉強をしない背景には様々な要因が考えられますが、実は親自身にも影響を与える理由が存在するかもしれません。
さて、親に見られる特徴にはどのようなものがあるのでしょうか。
「うちの子は勉強ができない」と言う
勉強が得意な子供は、自分に自信を持ち、その自信が学びを続ける原動力となっています。しかし、勉強が苦手な子供は、自分に勉強の能力がないと思い込んでしまうことが多いのです。
親が外で「うちの子は勉強ができない」とか「記憶力が悪い」とつぶやくと、子供がその言葉をどこで耳にするかわかりません。周りの人が「うちの子は勉強ができない」と話しているのを聞くことで、さらにやる気を失ってしまうことがあります。
人はどうしても相手の欠点に目がいきがちですので、その点については十分に気をつける必要があるでしょう。
「勉強しなさい」と口うるさく言う
毎日のように「勉強するべきだ」と何度も言ったり、勉強をしないことで叱責したりするのは、実は逆効果になることがあります。
子供がやる気を出す手助けをすることは確かに大切ですが、あまりにも頻繁に口うるさく注意をすると、逆に勉強に対する意欲が減ってしまったり、嫌いになったりすることがあります。そうなると、苦手意識が強くなりがちです。
親の期待に応えようとして勉強しても、結果が伴わないと次第にネガティブな気持ちになってしまうのです。

スマホ依存症
親がスマホを手放さない場合、子供もそれが普通だと感じるようになります。
子供は周りの大人の行動を見て学ぶため、親がスマホに依存している姿勢には特に注意が必要です。
常にスマホを触っている親から「勉強しなさい」と言われても、子供にはその言葉が響きません。親がスマホを見ている姿を見ていると、子供も勉強をする気を失い、成績が上がりにくくなることが多いのです。
子供の学力は母親次第?両親にできる4つの対処法
子供の学力はどうすれば上向きになっていくのか、やはり親の協力は不可欠ではないでしょうか。
両親にも出来ることは有りますのでいくつか考えてみましょう。
親子で一緒に取り組む姿勢を育む
「子供を変えないといけない」という考えは捨てましょう。
他人を変えようとするのではなく、まずは親自身が変化し、その姿を子供に示すことが大切です。そして、親子で一緒に学ぶ姿勢を育てることが重要です。
親が学ぶ内容をしっかり確認し、自らも学び直す意欲を持って取り組んでみましょう。
一緒に学習計画を立てたり、子供が集中している時にはそっと見守ることが大切です。
親が共に学ぶ姿勢を示すことで、子供は安心感を得て、学ぶ意欲が高まるでしょう。
子供が勉強する環境を整える
子供が勉強したいと思える環境を作ってあげましょう。
まず第一に、子供専用の勉強机をリビングに設置してみてください。さらに、子供が勉強に取り組んでいる時は、親もスマートフォンを触らないなど、周囲の環境を整えることが大切です。こうすることで、子供が勉強に集中しやすくなります。
また、周りに物が多いと、集中力が妨げられることがあります。勉強をする際には、視界に入る情報をできるだけ減らす工夫をすることが重要です。これにより、子供が勉強に向かう際の distractions を最小限に抑えることができるでしょう。
このように、環境を整えることで、子供は自然と勉強したいという気持ちが芽生えたり、勉強する習慣を身につけたり、集中して取り組むことが可能になるのではないでしょうか。
勉強する時間・量を決める
親から遊びと勉強の両立について教えることは重要です。ある程度勉強する時間や量を決めておくのが良いのではないでしょうか。
「○時から○時までは勉強して、それ以外は遊んでも良い」
「今日は○ページまで頑張ろう」
など、目標が数値で分かる事で、よりモチベーション高く勉強に取り組むことができますし、実践し繰り返すうちに勉強する習慣がつくようになるのではないでしょうか。

子供を伸ばす言葉をかける
子供が次回も学ぼうと思えるような言葉をかけてあげましょう。
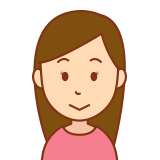
「すごく頑張って勉強してたね、でもここはちょっと間違えてしまったけど次はきっとできるよ!」
「自分から勉強を始めたのは良かった!」
「いつも応援しているからね!」
できないことを責めたり、他の子と比較するような言葉は、子供を萎縮させてしまうだけです。まずは、小さな成長を認めてあげることで、子供の自己肯定感を高めることが大切です。
自分自身が子供の頃に嬉しかった言葉を思い出して、それを子供にかけてあげることをおすすめします。
まとめ
勉強ができる親の多くは子供をとにかく褒めて否定的な言葉を使わず、子供の自主性を育て親子でのコミュニケーションが活発です。
子供が勉強できない事、しない事を責めるような言葉をかけるのではなく、子供と一緒に成長するぐらいのつもりで親として出来ることをフォローしていくのはいかがでしょうか。



コメント